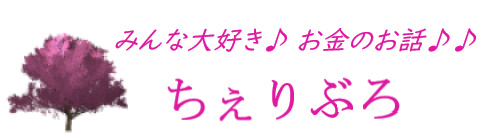前ページ 投信(16)上場投信 ETFの仕組みと投資信託との違い
次ページ 投信(18)上場投信 不動産投信(REIT)の全体像と使い方
この記事では、ETFのデメリットやそれを補う使い方のお話をしています。
目次
通常タイプのETFのメリットとデメリット

株式と比べてのお話です。
指数取引きは分散投資をするため、株式と比べると「値動きが少ない」というデメリットがあります。
日経平均など非常に馴染みのある投資対象なのに、この値動きが少ないというデメリット1つで、魅力が大きく削がれてしまっています。
値動きが少ないため、通常の使い方をする限り、短期投資にはあまり向かない商品かと思います。
次に、同じ指数を対象にした投資信託と比べてのお話です。
後述しますが、信用取引で建てられるという点が、投資信託と比べた場合の、ETFの最大のメリットだと思っています。
株式指数は朝と午後では、大きく価格が違う事もあるため、その時の時価で取引き出来る点はメリットと言えます。ただし、長期投資前提ならば、それほど大きなメリットとも言えません。
証券会社の口座を1つ持っておけば、どのETFも買える点はメリットと言えます。
投資信託はパッシブ(インデックス)型とアクティブ型がありますが、ETFはすべてパッシブ(インデックス)型です。
テーマに投資するような投資信託は、ほとんどがアクティブ型なので、ETFにもテーマ型はありますが、選択肢は非常に限られます。
海外にはアクティブ型のETFもありますので、いづれ日本でもアクティブ型のETFが組成されるかも知れません。
レバレッジ型とインバース型 メリットもデメリットも大きな商品です
ETFや投資信託には、指数の2倍3倍の値動きをするレバレッジ型や、指数と逆の値動きをするインバース型があります。投資信託の場合は、ブル型ベア型などと言います。オプションの場合は、コール・プットです。さらに、指数の2倍3倍の逆の値動きをするレバレッジの掛かったインバース型もあります。
指数取引きは「値動きが少ない」というデメリットがありますが、レバレッジ型はそのデメリットを解消してくれる商品です。
インバース型は、信用取引を利用出来ない人にとっては、数少ない下げ相場に積極的に対応出来る商品です。
レバレッジ型もインバース型も非常に魅力的な商品なのですが、大きな欠点もあります。
相場が騰落を繰り返す度に基準価額が毀損していく仕組みのため、中長期保有に圧倒的に向かない点です。短期向けの商品と言えます。
短期向けの商品の場合、終値でしか取引き出来ない投資信託(ブルベア投信)は、はっきり言って不向きです。レバレッジ型・インバース型ならばETFが良いと思いますが、急激に株価が動いている時は、ETFの理論価格と取引価格にズレが生じ易いので注意して下さい。
レバレッジ型・インバース型は、短期投資と割り切れないのならば、利用するべき商品ではないと思います。
ETFはどんな人に向く?株は?投信は?FXは?
株式投資は、全体相場、業界動向、そして個別銘柄の情報などを情報収集する必要があります。
個別銘柄への投資は、同じ相場でも、より状況にマッチした銘柄や、投資信託では考えられないような値上がりをする銘柄に出合える事もあり、たいへん魅力的です。
しかし一方で、個別銘柄への投資をメインにすると、日経新聞や専門誌、専門サイト、企業のHPまで見る必要が出てきます。やらなければならない事のリストが一気に跳ね上がってしまいます。
投資信託やETFであれば、全体相場を把握していれば投資出来ます。もう少し細かくやりたければ、業種別のETFやテーマ別の投資信託もあります。
「個別銘柄をするほどの時間はない」或いは「知識的に心配だ」という人は、投資信託かETFが良いと思います。
もちろん、投資信託やETFをメインにして、欲しい株主優待のある銘柄を買うとか、「閃いてしまった」株の銘柄に投資してみるというのは有りだと思います。
投資信託は、数ヶ月~数年の、長期保有を考えている人に向いています。また、積立てと相性が良いのも投資信託です。
投資対象では、テーマ別の投資対象を選びたい時には、ETFよりも投資信託の方が遥かに充実しています。
ETFは、商品内容は投資信託と似ていますが、使い方としては、投資信託よりも株式に近い商品です。株式のように売買を楽しみたい方、いづれは個別銘柄投資もやってみたいと思っている方に向いています。
因みに、株式と為替のFXで、向いている投資方法に違いがあります。
株式は、ボックス圏の動きからブレイクする相場を取りに行くのに向いていて、FXは、ブレイクせずにボックス圏に収まる相場を取りに行くのに向いています。
どちらも、それでなくてはダメという訳ではありませんが、もし、ボックス圏内に納まる相場を取りに行くのがお好きな方は、FXを試して見ても良いかも知れません。意外と相性が良いかも (^o^)
ETFは信用取引と組み合わせて本領発揮
通常のETFには、値動きの少なさというデメリットがあります。
レバレッジ型・インバース型のETFは、値動きの少なさを解消し、下げ相場にも対応出来るのですが、相場が上下する度に基準価額が毀損していくため、短期で決着を着けなければいけないというデメリットがあります。
このそれぞれのデメリットを解消する方法として、ETFを信用取引で建てる方法があり、お勧めです。
信用取引のコストは掛かりますが、相場が上下する度に基準価額が毀損していくというデメリットはなくなります。
やり方としては、1つは、通常のETFを素直に信用取引で、買建て、売建てする方法です。
もう1つは、ETFの基準価額が毀損していくというデメリットを逆手に取って、信用買建ての代わりに、インバース型の売建てを、信用売建ての代わりに、レバレッジ型の売建てをする方法です。売建てなので、基準価額が毀損する事はメリットになります。
ただし、信用取引の売建てをする時には、貸借倍率に注意して下さい。逆日歩が付くと思わぬ損をする事があります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
レバレッジと空売りを毛嫌いする人に
投資家の中には、レバレッジを掛ける事や売建てをする事を、毛嫌いする人がいます。「危ないだろ!」と。また、素人に止めるように勧める人も少なくありません。
しかし、レバレッジや売建てが危険なのは、技術の問題よりも、性格や慣れの問題の方が遥かに大きく影響します。
もちろん、まったくの素人の段階でやるべきではないと思いますが、なるべく早いうちに、レバレッジや売建てには慣れて置くべきだと思います。
投資のために用意した資金を、常に目一杯買付けてしまわないと気が済まない人がいます。見通しの悪い道路も障害物のある道路も、常にアクセル全開で行くような感じです。
この人の自動車に、2速3速のギアを付けたら大変な事になるでしょう。スピードが出る分、大事故です。ギアを付ける事がいけないのでしょうか? いいえ、アクセルを抜く事を覚えなければ、遅かれ早かれ事故を起こして退場する事になるでしょう。
そして、危険を察知してアクセルを抜く事を覚えれば、見通しの良い道路でギアを上げて、無理をせずに距離(利益)を稼ぐ判断が出来るようになります。
売建ても、目一杯やってしまう人に権限を与えたら非常に危険です。まず、売建てを目一杯やる事が、如何に危険か理解する必要がありますが、理解したなら慣れておく必要もあります。
売建ては、下げ相場で利益を取れる代表格の投資方法です。「上がるも相場、下がるも相場」と申します。売建て無しで投資をする事は、大きなハンディを背負って取引きをするようなものです。経験の浅い者が、大きなハンディを背負って勝てるでしょうか。早いうちに慣れるべきです。
次回は、上場投信の不動産投信(REIT)です。
-

-
投信(18)上場投信 不動産投信(REIT)の全体像と使い方
上場投信のうち、不動産を証券化したものを不動産投信(REIT)と言います。この記事では、不動産投信(REIT)の全体像と使い方について話しています。
-

-
投信(16)上場投信 ETFの仕組みと投資信託との違い
ETFとはどういうもので、投資信託とは何が違うのか? 対象指数はどんなものがあるのか。上場している事によって、取扱い金融機関、価格の決まり方、売買出来るタイミングなどがどのように違うのか などを説明します。