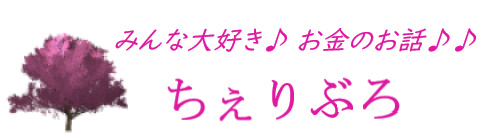次ページ 投信(2)投資信託の5つの魅力とメリット
目次
投資信託(ファンド)とはどんなもの?

投資信託は、投信、ファンドなどとも言います。
ここでは、あまり細かな例外とかに捕らわれず、ざっくりと投資信託という商品について説明したいと思います。
投資信託の特徴は、何と言っても分散投資です。それぞれの投資信託にはテーマがあり、そのテーマに沿った投資対象に分散投資します。テーマは、例えば、スマホ関連とか、コロナ関連とか、日経平均、ブラジル債券など様々あります。そして、投資対象や運用方針によって、投資信託は全くの別物になります。
募集する側の具体的な流れは、予め投資方針(テーマ)や条件を決めて募集を掛け、不特定多数の投資家から資金を集めます。そして、集めた資金を運用し、損益を投資家に還元します。儲かる事もあれば、損する事もあります。
様々な投資対象に、様々な切り口で、年間500本近くが新規に募集されており、現在6000本近くの投資信託があります。
信託期間(運用期間)は、10年程度が多く、短いものでは3年程度、長いものでは無期限のものもあります。途中換金出来ないファンドは別として、償還までの期間が長いのは、「それまでの間の良いタイミングで換金して下さい」という意味合いに取って頂いて良いと思います。償還まで持ったからと言って良い事はそれほどありませんし、途中換金に対するペナルティもそれほど大きくありません。
目論見書・販売用資料・運用報告書の役割り

個別の投資信託の内容を知りたい時には、目論見書を見ます。さらに、新規に設定された投資信託ならば販売用資料、運用開始後、何ヶ月か経っている投資信託ならば月次レポートなどの運用報告書を見ます。
目論見書の記載内容と役割り
目論見書とは、その投資信託の投資判断に必要な重要事項を説明した書類の事で、投資信託説明書とも言います。最近の目論見書は図解入りで見やすくなっています。
目論見書には、その投資信託の「予め決められた投資方針や条件」を解りやすくするために、投資信託協会で定めた商品分類や属性区分・ファンドの目的・特色というものが記載されています。
それぞれの内容はこんな感じです。
商品分類の一覧です。おおまかな投資対象やファンドの形態などが記載されています。
| 商品分類表 | ||||
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 | 独立区分 | 捕捉分類 |
| 単位型 追加型 |
国内 海外 内外 |
株式 債券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
MMF MRF ETF |
インデックス型 特殊型 |
上の表は一覧ですが、実際にはこんな感じで掲載されます。(例)
| 商品分類表 | ||||
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 | 独立区分 | 捕捉分類 |
| 追加型 | 国内 | 株式 | インデックス型 | |
属性区分の一覧です。商品分類をさらに細かく分類しています。
| 属性区分表 | ||||||
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 |
年1回 年2回 年4回 年6回 年12回 日々 その他 |
グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 エマージング |
ファミリーファンド ファンド オブ ファンズ |
あり なし |
日経225 TOPIX その他 |
ブルベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 |
こちらも、こんな感じで掲載されます。(例)
| 属性区分表 | ||||||
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
| 株式 中小型 | 年2回 | 日本 | ファミリーファンド | なし | TOPIX | |
ファンドの目的・特色では、商品分類や属性区分で伝えきれないファンドの投資方針や手法などを文章でわかりやすく説明しています。
その他にも、リスクやコスト、運用実績など投資判断に必要な事が記載されています。1つ注意していただきたいのは、フォントの大きさです。昨今、目論見書に限らず、リスクが非常に目立つように書かれています。リスクを喚起するという意味では良い事なのですが、さほど大きくないリスクや、滅多に起こらないリスクもデカデカと書かれているため、取って良いリスクなのか取ってはいけないリスクなのか、かえって判断が難しくなってしまっています。
時々、「目論見書に全て書かれている」などと聞きますが、そんな事はありません。目論見書だけではわからない事もあります。
例えば、今の相場見通しに合った投資信託が設定されたとします。投資信託は長期間運用するので、当初建てた見通しどおりに事が運ぶとは限りません。しかし、目論見書に事細かく運用方針が記載されていたら、状況の変化に対応した運用がしづらく、或いは出来なくなってしまいます。目論見書に記載されている事は、護らなければならない約束事だからです。その為、目論見書にはかなりの程度の幅を持たせた運用方針が記載されています。同じような投資対象のファンドでも、それぞれのファンドには、こだわりのポイントがあるものなのですが、目論見書だけでは皆同じに見えてしまうのはその為です。
細かな違いがわかる販売用資料や運用報告書
販売用資料
販売用資料は、投資信託が新規に設定された時に作られ、その投資信託の設計者や運用担当者のこだわりのポイントが、魅力的に綴られています。販売するための資料ですから。普通の商品に例えると、目論見書が仕様説明書、販売用資料がカタログといったところでしょう。カタログの方がわかりやすいですよね。
運用報告書
運用報告書は、設定後の運用状況を運用担当者が月次レポートなどの形態で報告している報告書です。ここには、運用担当者が今現在の相場をどう捉え、どういう売買をしたかなどの情報が記載されているため、目論見書ではわからない、似たような投資信託との違いがわかります。
また、評論家ではないプロのプレイヤーが、先月の取引きを理由付きで報告しています。見たことのない方は1度見てみる価値はあると思います。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投資信託の購入金額・運用総額の上限・下限

購入単位の下限額は、ネット証券では100円から買える証券会社もあり、大手証券やメガバンクなどでは1万円前後からです。積立ての場合は、ネット証券では100円から買える証券会社があり、大手証券やメガバンクなどでは1000円からとなります。証券会社によって違います。上限額もファンドや証券会社によって決まっている場合もあります。その場合は、数千万円~数億円位でしょうか。これは、1度に大量の買付け、若しくは解約が出ると運用上支障をきたす場合があるからです。
ここで説明している投資信託は公募投資信託ですが、数億円などのまとまった資金で買付けたい場合、同じ投資信託を私募形式で設定するサービスなども、証券会社によっては行っている場合があります。私募形式で設定すると、買付け単価(簿価)を10,000円に調整出来るため、法人の運用などに便利です。
ファンド全体の運用総額には、下限額と上限額が設定されています。下限額は新規募集時で10億円位から、上限額は100億円位からほぼ上限額のないものもあります。こちらは、目論見書に記載されています。
募集段階で下限額を下回る事は滅多にありませんが、その場合は募集中止になったりします。運用している間に解約や値下がりで下限額を下回って来た場合は、繰上償還(早期償還)される事もあります。同様に募集段階で上限額を越えて来ると、それ以上の新規募集及び、暫くの期間追加購入が出来なくなる事もあります。運用期間中に上限額を越えて来た場合は、同様に追加購入出来なくなる場合と、上限額が引き上げられる場合があります。
上限額は、対象商品の市場規模が大きく関係します。例えば小型株のファンドなどでは、小型株の市場規模も小さいですし、組み入れる個別銘柄も、発行済み株式数や出来高が少ない為、上限額は小さくなります。逆に米国債のファンドなどでは、数千億円でもびくともしないため、上限額はほぼありません。
以上、投資信託の大まかな商品内容でした。
次回は、投資信託の魅力とメリットについてです。
株式の基礎知識の個人ブログを探すなら

基礎知識(株)ランキング
お金(投資)の個人ブログを探すなら
![]()
にほんブログ村
-

-
投信(2)投資信託の5つの魅力とメリット
投資信託の魅力やメリットは、大きなもので5つあります。1. 詐欺の心配をしなくて良い 2. 様々な対象商品やテーマ 3. 良い運用はずっと続く? 4. 分散投資 自分ですると大変 5. 少額投資は結構重要です。